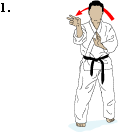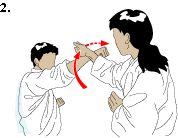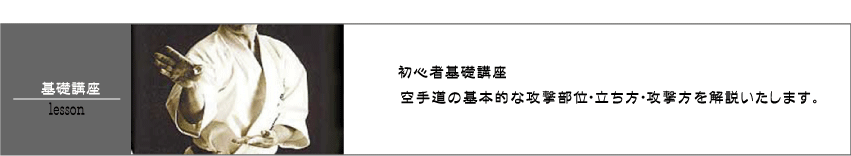
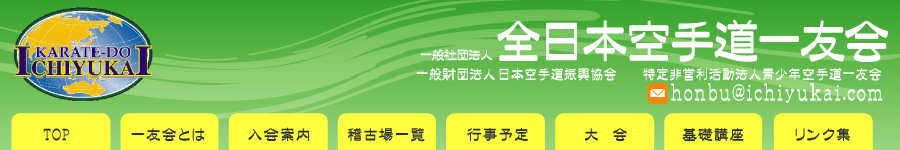
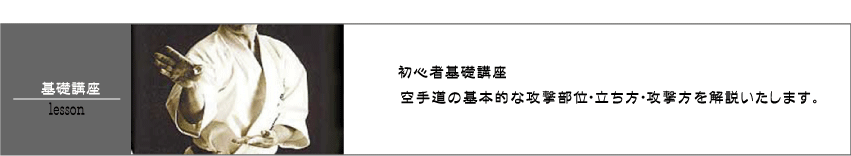
●基礎講座メニュー
| 基本 | |||
|---|---|---|---|
| ●攻撃部位 | ●立ち方 | ●攻撃技 | ●受け方 |
| 形 | |||
| ●形とは | ●太極上段 | ●撃砕第一 (形の分解) | |
●基本-受け方
上段受け(上受け)
1. |
右手を前方に折り曲げ、中段に構える。 肩の力を抜いて右上わきを絞め、ひじを体の内側に入れる。 ひじと体とのあきはこぶしが1つ入る程度、こぶしの高さを肩よりやや低めにして構える。 引き手のひじが正面から見えてはいけない。 |
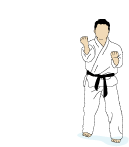 |
|---|---|---|
2. |
受ける方の手を前方に出し、引き手に戻る手と交差させる。 その時、受け手を引き手の外側で交差させ、手の甲を相手に向けている。 |
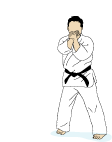 |
3. |
交差させた引き手は内側へ弧を描くようにして乳の下まで引き手を取り、 受け手はこぶしを徐々にねじりながら、手のひら側を相手へ向けるようにして ひじを上げながら斜め上段に受ける。 引き手と受け手の動きは同時に同じスピードで移動させる。 |
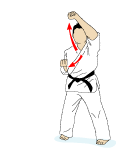 |
4. |
これは、突きと受けを組み合わせた図であるが、受け手は受けすぎてもよくないし、 受け損じてもいけない。 受けは腕の力で行なうのではないから、受けた時に肩に力が入ってひじの絞めが 甘くならないように気をつける。 突き、受けの組手原則は、右手突きに対して右手受けが望ましいが、 図ではわかりやすくするために右手突き、左手受けにしてある。 |
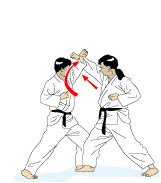 |
中段受け(横受け)
1. |
受けの構え。 |
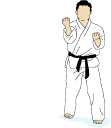 |
|---|---|---|
2. |
左引き手を右構え手のひじの下まで体に沿って移動させて受けの用意。 構え手は内側肩のあたりで受け手と交差させ引き手とする。 この時、受け手は外側に位置させ、こぶしをひじの下からねじるようにする。 |
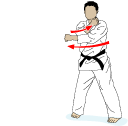 |
3. |
内側にある引き手はそのまま乳の下まで引き込む。 それと同時に左手の表小手部で相手の攻撃を横に受け流す。 受けはひじで弾くようにはせず、ひじを絞めながら相手の攻撃の手を事前に 手首で捕らえて引き込むようにして受ける。 受けの描く軌跡は、真横への直線ではなく、内から外へ弧を描くようになる。 |
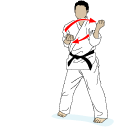 |
4. |
突き、受けの組み合わせであるが、受けた時の受け手の位置は、 ひじと体の間にはこぶしが1つ入る程度、こぶしの高さは肩からやや低め、 こぶしの横の位置は、こぶし半分が自分の体から横に出る程度で止める (受けの構えと同じ)。 |
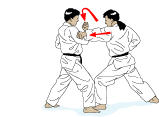 |
下段払い(払い落とし)
1. |
受けの構え。 |
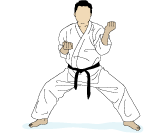 |
|---|---|---|
2. |
受け手を上段に振りかぶり(手の甲を相手側に向ける)、 引き手を受け手のわきの下に移行させる。 |
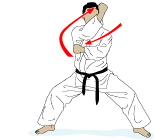 |
3. |
左引き手が乳の下へ引き込まれるのと同時に、 受け手は正面をこぶしが弧を描くようにして丸く受ける。 受け手は上から下へまっすぐに落とさないで、横に受け流すことを忘れてはいけない。 受け切った受け手の位置は体から少し外側に出る程度で止め、 こぶしと腕とは弓なりになっており、ひじ関節で力の調節を計るようにする。 |
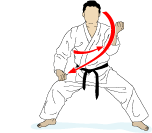 |
4. |
突きと受けの組み合わせ。裏小手で受ける下段払いは、 相手の背小手を受けるのではなく、裏小手を横に受けることを忘れてはいけない。 |
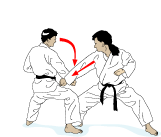 |
掛け受け
1. |
掛け受けの構え。 左手をこぶしにして受けの構えをつくってから(上段受けの構えを参照)、 同じ位置で開手にする。手は親指を曲げて手刀のように開き、 手のひらを小指側に直角に曲げて相手の方に向ける。右手は手刀で水月をカバーする。 |
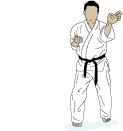 |
|---|---|---|
2. |
カバーしている右引き手を、中段受けと同じように左手のひじの下から前方で 弧を描くようにして左手と交差させる。 この時、受けるほうの右手は左手の外側を通し、引き手に戻す手は、 内側を通すようにする。 |
 |
3. |
左手を水月カバーに戻すと同時に、右手は手のひらを相手に向けたまま 手首を左から右へ折り曲げるようにして前方で掛け、 手首の右側(小指側)で引っ掛けるようにして受ける。 掛け受けには図のように手首の左右への掛けだけで受けるものと、 手のひらを回転させて掛ける掛け受けひねりとの2種類がある。 掛け受けひねりは、図2の段階で手のひらを自分の方に向け、 3の掛けの時には手をひねって小指側で掛け、手のひらを相手側に向けるようにする。 |
|
手刀受け
1. |
掛け受けの構え。 |
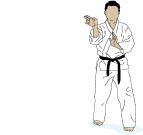 |
|---|---|---|
2. |
受け手となる左手を、右の肩のところまで内側から移動させる。 この時、手のひらは自分の方に向ける。 |
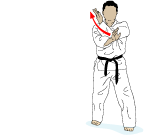 |
3. |
受け手を手首を斜めにしたまま半回転させながら、切るようにして前方に押し出す。 受けるところは手刀部であるが、相手の攻撃を内側から外側へ 側面を押し戻すようにして受ける。 腰は受けた方へ入り、肩と腰とが並行になっていなければならない。 引き手は手を開いてわきの下まで引くが、水月をカバーして次の攻撃に備える。 |
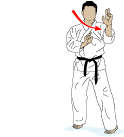 |
4. |
これは突き手と受け手の組み合わせの図であるが、 受ける場合、突き手のひじを側面より受けるのが効果的である。 この受けは、掛け受けのような曲線の受けではなく、直線的な受けである。 |
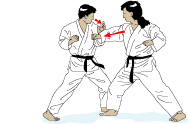 |
中段下払い(横受け下払い)
1. |
受けの構え。 |
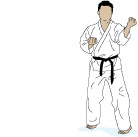 |
|---|---|---|
2. |
構えている左手のひじを基点にして、内側に下段払いをするようにして下げる。 右引き手は左手に合わせながら前方に出し、左手と交差させる。 この時右手は外側で交差させ、下げる方の手が内側を通るようにする。 |
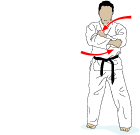 |
3. |
右手中段受け、左手下段払い。 |
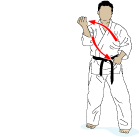 |
4. |
左手で中段受け、右手で下段払い。 両手で同時に受ける両手受けの一種であるが中段受けと下段払いの混合受けである。 受ける部分は中心線(水月)であるから、両手を縦に移動させるのではなく、 中心線に向かって交差させることが大切である。 この受けは中段、下段を同時に受けるだけでなく、 一方の受けと同時に他方を牽制カバーする意味でも用いられる。 |
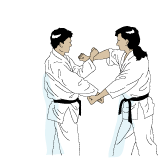 |
回し受け(巴受け)
1. |
右手を中段受けの構えから開手し、手のひらを上に向ける。 左手は、開手のまま手の甲を右ひじの下にそろえる (慣れたら掛け受けの構えから始める)。 |
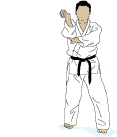 |
|---|---|---|
2. |
右手はひじを基点として内側に下げる。 その時、手のひらはできるだけ相手の方へ向け、親指側手首で受ける。 左手は外側を通して右手と交差させる。 |
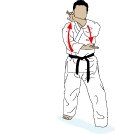 |
3. |
右手で中段を受けると同時に、左手は上段を小指側掛け受けで受ける。 |
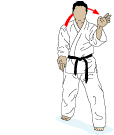 |
4. |
左右の掛け受けは前方で円を描くようにして受けるが、 左手は上段を受けて下段へ、 右手は中段を受けて上段へ戻す。 回し受けは受けだけの技ではなく、受けた後の底掌による攻撃をひかえた 受け技であり、4の受けが終わってから右手で鎖骨部、左手でそけい部への 底掌突きも可能となる。 また、両手同時の受けとしてだけでなく、いずれか一方のみとして利用することもできる。 |
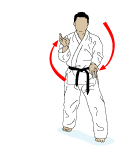 |
底掌受け
1. |
相手の突きに対して上から底掌で落として受ける形で、 手首の上下のスナップを利かせて相手の背手部を叩くようにして受ける。 |
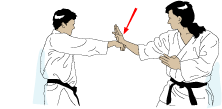 |
|---|---|---|
2. |
相手の突きを下から上へ底掌で突き上げて受ける形。攻撃者の手首を痛めさせる。 |
 |
3. |
突き攻撃を、横から底掌のスナップを利かせて受け流す受けである。 |
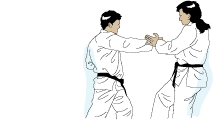 |
4. |
蹴りの攻撃に対する底掌の押さえ受け。 この受けは、受けるというよりも出足を押える形で、攻撃的防御といえる受けである。 |
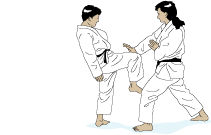 |
内小手受け
突き攻撃に対して裏小手部で内側に受け流す受けである。 小手ではじくようにしないで相手の力を流し、 3で相手の小手に触れると同時に腕と手首を内側にひねって突きの力をそらせるようにする。 |
|
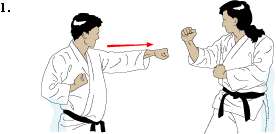 |
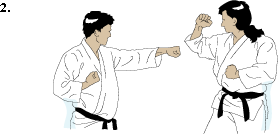 |
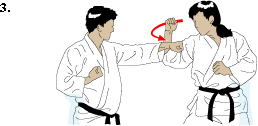 |
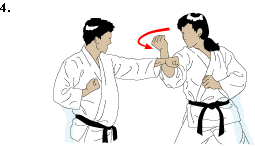 |
すくい受け
すくい受けは、蹴りや突き攻撃を下からすくい上げるようにして受ける方法で、手のひらを使用する。 相手の蹴りを受ける場合は、手ですくうと同時に体をひねりながら蹴りの目標外に逃げて受けなければいけない。 図2は受けた瞬間で、図3はすくった状態である。 なお、図4のように押し蹴りになった相手の引き足を捕まえて、すくい上げることもできる。 すくう場所は後ろ踵とアキレス腱の部分がよい。 |
|
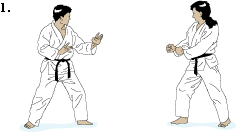 |
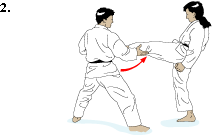 |
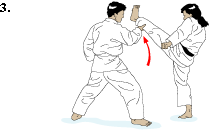 |
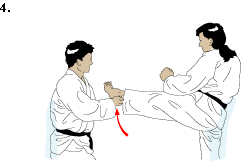 |
十字受け(交差受け)
十字受けは両手を交差させて受ける方法で、1本の手では受けられないような力の強い突き、蹴りなどに対して使用し、 図のように上段を受ける方法と、下段を受ける方法とがある。 受け方はこぶしを握って受ける場合と、開手で背拳によって挟み込む受けとがある。 受けは相手の攻撃より先手を取って受けることが望ましいので、前進しながら相手の懐に飛び込み、 相手の突き手の先端より少しでも手のつけ根よりの方を受けるようにするのがよい。 |
|
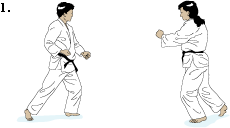 |
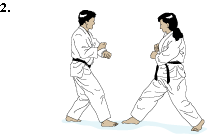 |
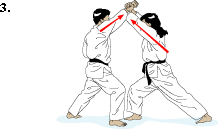 |
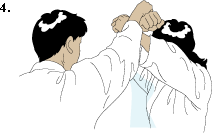 |
添え受け
十字受けと同じように、強い力の攻撃の場合に確実に受ける方法である。 強力な突きを受けた時に、一番負担のかかるところは受けてのひじである。 ひじの力が緩むと、その突きを受けきれないために、体で受けることになりかねない。 したがって添え受けは受ける手のひじの部分を他方の手で押え、補強する方法である。 受け方は添え手のない中段受けと同じだが、少しでも相手の力を利用する意味で、はじくようにして受けずに、 相手の突きを体より遠い位置で受け始め、突きと同時に受け流し相手の力をそらせるようにするとよい。 |
|
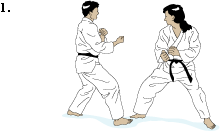 |
2.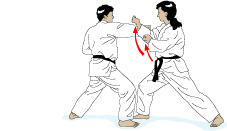 |
3.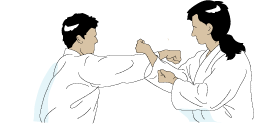 |
4.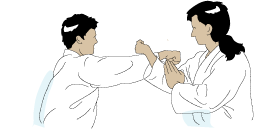 |
足底払い受け
数少ない足で受ける受け方の1つであるが、基本受けよりも自由組手などに使用される実戦的な受けといえるものである。 1の構えから2の相手が蹴ってきた時、3のように後ろ足の足底部で相手の蹴り足の膝を横から回すようにして払い受ける。 受けが効果的に決まった時には、図4のように相手の態勢が受けの反動で崩れて背中を向ける状態になる。 蹴りを足で受けるには、相手の蹴りのスピードに合わせなければならないのでタイミングが難しい。 |
|
1.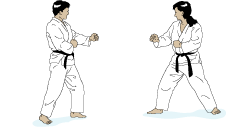 |
2.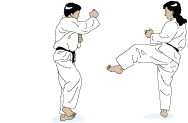 |
3.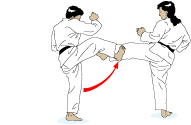 |
4.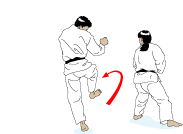 |
足棒掛け受け
足底払い受けと同じように実戦的な受け方で、剛柔流のような接近戦の多い空手では利用価値のある受け方である。 この受けは受けと同時に攻撃的な要素も含まれており、攻撃を仕掛けた相手側にダメージを与える事もできる。 また、受けた後の姿勢が防御側にとって有利な態勢となるため反撃のチャンスとしても有効的である。 |
|
1の構えから2で相手が蹴り始めるのと同時に受けの態勢にはいり、3のように相手の蹴りが伸び切る直前に (すなわち、まだ足に力が入っていない状態の時に)膝もしくは下肢部で蹴りを押えるようにして受ける。 4は相手が蹴りを断念して着地すると同時に、受け足も攻撃側の引き足にそろえて逆に前進し、攻撃可能な間合いまで接近する。 蹴りを受ける場合、足が伸び切った時に受けることは受け手の不利になるから、できるだけ早く受け止めなければならない。 |
|
1.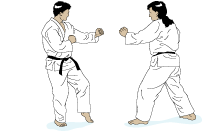 |
2.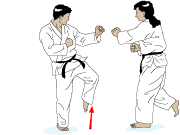 |
3.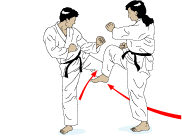 |
4.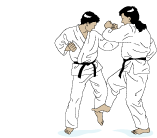 |
鶴頭受け
これは鶴頭部で受ける方法で、上段、中段が可能である。 鶴頭受けはスナップの反動を利用することから、受けのタイミングが要求される。 |
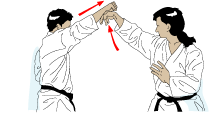 |
底掌押え受け
足棒掛け受けと同じように、相手の攻撃直前に1歩前進して相手の足か膝を底掌部で挟むようにして押える。 |
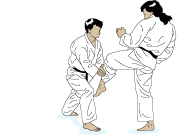 |
足首掛け受け
蹴り攻撃を体の転身で受けると同時に、蹴ってきた足の裏側(アキレス腱側)を背足部で引っ掛けるようにして受ける。 これは相手のバランスを崩す時に使用される。 |
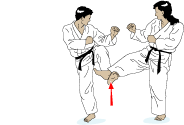 |
足刀押え受け
相手が蹴り始めるのと同時に接近し、相手の蹴り足を足刀で押える方法で、 受けるだけでなく、蹴りを出させない牽制の手段としても使用できる。 これは出会いを封じる形となることから、試合などにおいては禁止技として注意を受けることもあるが、 相手の心を事前に察して封ずる方法としては効果的である。技としては大変難しいことから、初心者の使用技としてはすすめられない。 |
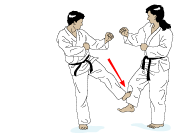 |