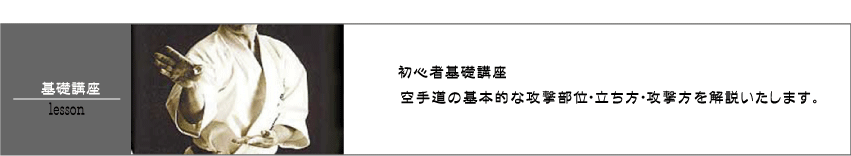
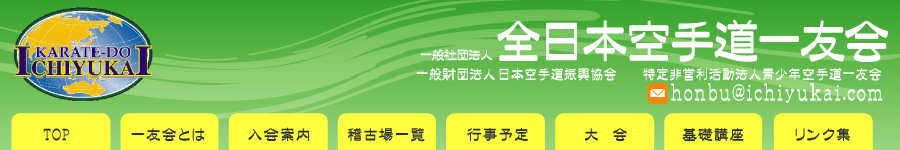
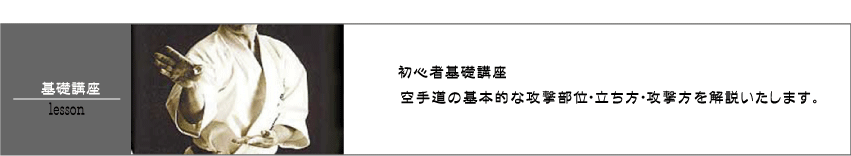
●基礎講座メニュー
| 基本 | |||
|---|---|---|---|
| ●攻撃部位 | ●立ち方 | ●攻撃技 | ●受け方 |
| 形 | |||
| ●形とは | ●太極上段 | ●撃砕第一 (形の分解) | |
●基本-攻撃技
(1)突き技
▼正拳突き(上段)
1. 正拳突き の構え |
左右の手をこぶしに握り、左手を突いた状態にまっすぐ伸ばす。 右手はあばらの下(乳の下)まで引き手を取り、突きができる状態に構える。 |
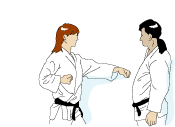 |
|---|---|---|
2. 正拳突き 上段 |
人中に対して正拳突き。右手で上段への正拳突きを行う。 ひじで体をこするようにして、まっすぐ突く。こぶしのひねりは、 突きはじめから自然にねじり始め、突ききった時にはこぶしは まっすぐでなければいけない。目標が引き手の高さより高い位置なので、 突く時に肩に力が入ったり、ひじの絞めが甘くなりがちであるから、 注意を要する。 突き切った時に肩が前へ流れていたり、こぶしが曲がったりしてはいけない。 |
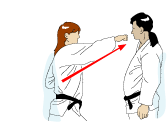 |
▼正拳突き(中段)
1. 正拳突き の構え |
正拳突き上段と同じように左手を前にして正拳突きに構える。
|
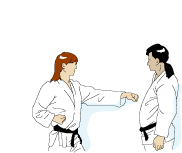 |
|---|---|---|
2. 正拳突き 中段 |
上段突きと同じ要領で突き出すが、 目標が水月であるから引き手からまっすぐ前方に突く。 |
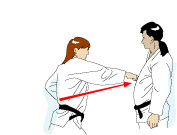 |
▼正拳突き(下段)
1. 正拳突き の構え |
正拳突きの構え。 |
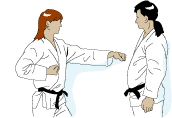 |
|---|---|---|
2. 正拳突き 下段 |
右引き手を目標の下腹もしくは金的に対して突き落とすようにして突く。 下段は引き手の位置よりも低い目標であるから、 押し突きにならないように気をつける。 突ききったとき背手とこぶしとが直角になっていなければいけない。 これは上段、中段、下段とも共通なことである。 また突きの軌道も、目標と引き手のこぶしとが直線で結ばれるように突く。 |
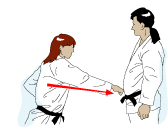 |
▼正拳逆突き
1. |
正拳突きは、いかなる立ち方においても行なうことができ、 名称は全て「正拳突き」と称するが、足と手とが逆になった状態での 正拳突きを「正拳逆突き」と称する。 |
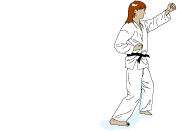 |
|---|---|---|
2. |
突き方その他の注意は全て正拳突きと同じであるが、 図は左三戦立ちの上段突きの構えから、 中段の正拳突きを手足逆にして突いている姿勢である。 逆突きは、正常な突きと比べて腰の回転がきくので、 スピードを上げることができ、腰の回転内で突きを止めれば、 肩の流れを防ぐこともできる。 |
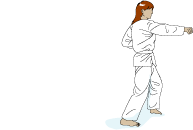 |
▼正拳下突き (これは手首のスナップを利用する突き方で、主として水月を目標とすることが多い。)
1. 正拳突き の構え |
構えは正拳突き(上段)と同じだが、 図では立ち方を変えて四股立ちであるので、 腰をひねった形になっている。 |
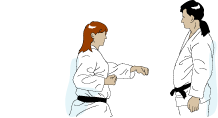 |
|---|---|---|
2. 正拳下突き |
正拳突きが手首をひねってこぶしの回転で突いているのに対して、 これはこぶしを回転させず、背手を下に向けたまま当たる直前に 手首を落とし、下から突き上げるようにして突く。 こぶしの軌跡は正拳突きと同じように直線であるが、 スナップをきかせすぎて下からのアッパーカットにならないように 注意すること。 |
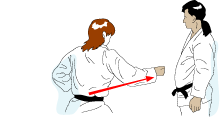 |
▼上げ突き・・・上げ突きは、相手のあごを下から上に突き上げる突き方である。
図1の構えから図2の突きまでの間隔は短いので、必要以上に突き上げる必要はなく、腋を絞めて肩が上がらないように注意する。 突いたこぶしは伸ばし切らないで、再び図1の構えまで戻す。すなわち、上下のピストン運動と考えてよい。 |
|
普通、引き手はこぶしを握るが、開手して手のひらを相手に向けるようにして水月部をカバーすることもできる。 突き上げの反動に対して、引き手を上から下へ、突きとは逆方向に力を働かせて力の平衡を保つ。 |
|
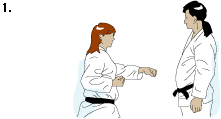 |
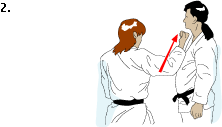 |
▼連突き(上段正拳突き2本)・・・
連突きとは正拳突きを連続して行なう突き方で、普通見本技としては(目標を複数としても)2〜3本の連突きである。
構えは平行立ちの姿勢で両手を両脇に下げる場合と、一方の手を水平に伸ばして突きの構えを取る場合とがある。 |
|
図2は、1本目の上段に対する正拳突きを、1歩踏み込んだ前屈立ちで行なっている。 図3は同位置における2本目の正拳突きである。 |
|
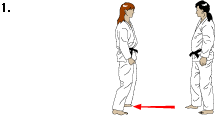 |
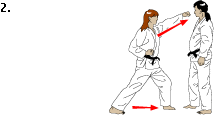 |
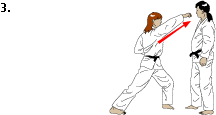 |
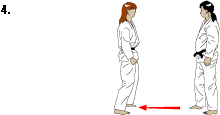 |
▼鉤(かぎ)突き ・・・正拳突き、下突きなどがまっすぐ突くのに対して、鉤突きは弧を描くようにして横から突き込む技である。
普通、正拳突きはひじが体をこするようにしてまっすぐ突くようにと指導しているが、鉤突きはひじが体から離れてから、 こぶしをねじりながらひじを外側に開き、目標に対して斜めから突くようにする。 |
|
この突きは片手によるものと、両手による方法とがある。 |
|
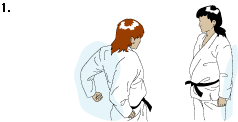 |
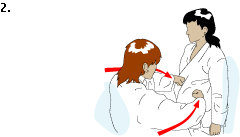 |
▼一本拳突き・・・
一本拳を使用して突く突き方で、その方法は正拳突きと同じである。 当てる部分が正拳と一本拳とが入れ替わったと
思えばよい。
一本拳突きの目標は正拳突きよりもより小範囲となるために、目標に対する方向づけをより正確に行なわなければならない。 図では水月を目標としているが、他にわき腹とかのどなどのように細かい急所への攻撃に適している。 |
|
なお、正拳突きのように半回転して図のように手の甲を上にする場合と、引き手から 1/4回転して突き、 こぶしを縦にする場合とがある。 |
|
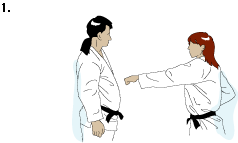 |
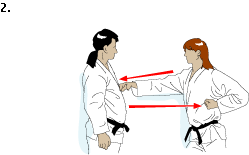 |
▼中高一本拳突き・・・一本拳突きの握り方を、中高一本拳に変えた突き方である。
中高一本拳も一本拳のように狭い急所への攻撃に適しており、こぶしの回転も 1/2回転、1/4回転と使い方を変えることができる。 また、相手に対して牽制的に突く場合には、こぶしを回転させずに縦拳で突くこともできる。 |
|
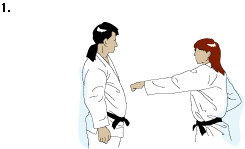 |
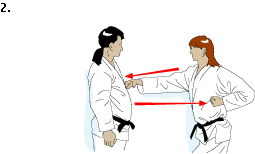 |
▼開甲拳突き ・・・こぶしの握り方を開甲拳として、正拳突きの要領で突いた場合を開甲拳突きという。
開甲拳は、指を思いきり曲げて、第3関節を背拳にそらせるようにして突かないと、突き指の原因ともなるから注意しなければいけない。 |
|
この突きは、一本拳や中高一本拳よりも実用的である反面、相手にケガをさせる場合も多いので、注意して練習することが必要である。 |
|
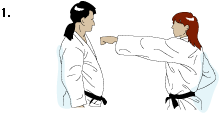 |
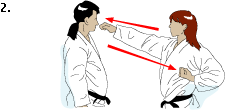 |
▼底掌突き・・・底掌部で突く突き方で、目標は主に顔面であるが、水月、鎖骨への攻撃にも使用される。
底掌突きは相手側に腕を直角に曲げ、底掌が腕と水平に当たるようにする。 攻撃の長さとしては正拳突きよりも短くなるが、突きの威力としては大きい。これは牽制的に使用する場合も多い。 |
|
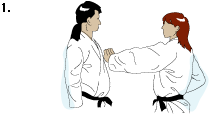 |
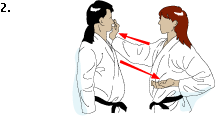 |
▼貫手突き ・・・
貫手突きは指の先端で突く方法であるが、指先の鍛錬をしていない者にとっては、この突きは意味をなさず、
かえってケガのもとになる。
目標は顔面、のど、水月など急所としては比較的柔らかく狭い部分を主として突き、 貫手の回転も 1/2回転、1/4回転などがある。図は1/4回転による水月への縦突きである。 |
|
貫手は各指の先端をまっすぐ伸ばして突く場合と、各指を先端部でそろえて突く場合とがあるが、 それは鍛練の方法によって異なるものである。 |
|
 |
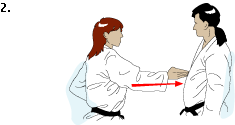 |
▼一本貫手突き・・・
1本指による貫手突きであるが、現在はほとんど練習されていない。特殊な者の特殊な練習としてだけあげられる突きである。
指1本による破壊力の弱さのため使用される目標も限定されるが、のど、目などの極力弱い部分にしか使用できない。 間違って骨の部分を突いたり、受けられた場合は逆に不利な状態となるから、使用することはあまりすすめられない。 試合などにおいては禁止技とされている。 |
|
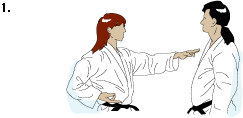 |
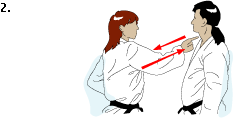 |
▼二本貫手突き(目つぶし突き)・・・
人さし指と中指による貫手で、目への攻撃としての突き技である。
突き方は他の突き方と同じであるが、上から下へ突き下ろすのではなく、下から上へ突き上げるようにする。
この技も、実戦としての使用は危険であることから、普段練習はせず試合などにも禁止技となっている。
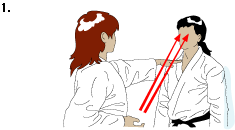 |
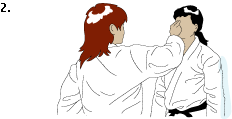 |
▼添え突き・・・
一方の手を補助として添えて突く突き方で、体重の小さい者が大きい者へ突くときとか、
重心を乗せて飛び込んでくる相手を、受け止めるようにして突く場合などに使用される。
図では、すり足で前進しながら技を行なっているが、定位置においても同じである。 |
|
突きとしての威力は、破壊力よりも重みのある突きとして効果がある。 |
|
1. 引き手は腋下におかず、やや前方に背拳を下に向けて構える。補助する手は突く方の手の上か下に位置させる。 |
|
2. 突き手は、普通の正拳突きの要領で突くが、補助手は突き手にぴったり密着させ、突き手に合わせながら同時に動かす。 |
|
突き切った時の補助手は、突き手の親指側手首を虎口部で押すように引っ掛け、手首が曲がらないように、 また、突き手による力を倍にする意味で支えるようにする。 |
|
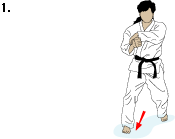 |
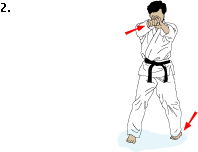 |
▼双手突き・・・両手で突く突き方にはいろいろあるが、それら全てを双手突きと称する。
図のものは基本的な例であるが、目標の上段と中段とを同時に突いている。 図2のように両手ともわきの下に引き手を取る。続いて左手を1/2回転させて上段突き、右手はこぶしを回転させずに中段へ下突き。 |
|
双手突きは突きとしてだけでなく、両手による受けと両手による引き取り、つかみ取りと組み合わせて使用する場合が多い。 突く目標も左右の鎖骨であったり、のどや水月であったり、いろいろに変化させて使用することができる。 形としては同時に突くが、実際に使用する場合は片手ずつ分けて突くか、片手を「受け」として、他方を「突き」とする等、 変化させる事もできる。 |
|
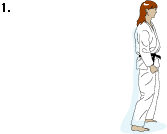 |
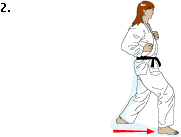 |
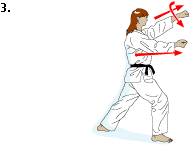 |
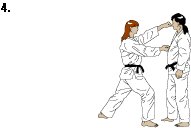 |
(2)打ち技
▼振り打ち・・・
振り子の原理と竹のしなりを利用した打ち技で、正拳部で相手のこめかみに攻撃する。
振り打ちの軌跡は突き技の直線とは異なり、曲線を描きながら手首のスナップによって打つ。
1. 振り打ちの構え。 突き技の引き手による構えとは異なり、こぶしを後方に隠し、背小手と背拳とがそるようにして背中に位置させる。 |
|
2. 攻撃と同時に、腰を正面にひねることによって背中にあるこぶしは振り子のように飛び出す。 こぶしは右方向へ曲線を描きながら振り込まれ、相手のこめかみに当たる直前に、外側に張られている手首を背小手方向へ 折り曲げてスナップをきかせる。 当たる部分は正拳部であり、打ち終わった時には手首、ひじが曲がっており背拳が 自分の方を向いていなければいけない。これはちょうど肩、ひじ、手首の3つが竹の節の役目を果たしており、 腰の回転力と節となる3ヶ所のスナップによって攻撃の加速と破壊力が生まれるものである。 |
|
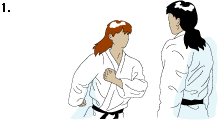 |
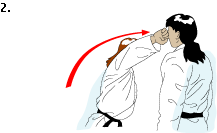 |
▼裏打ち(正面)
振り打ちのように、正拳部で手首のスナップによって攻撃する打ち方である。 振り打ちが横からの手首の返しであるのに対して、裏打ちは正面から前方へ手首をきかせて打つ。 左手を引き手にとって構え、その左引き手のこぶしで打つ場合と、前の右手こぶしで、スナップをきかせて打つ場合とがある。 裏打ちは近距離からの攻撃に適しており、破壊力の弱いわりには効果の大きい打ち方である。 |
|
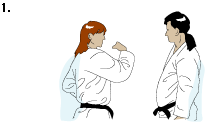 |
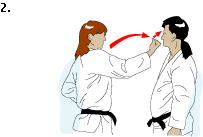 |
▼外手刀打ち・・・手刀部で攻撃する打ち方で、外側から水平に攻撃する技である。
1. 右手を上段横に振り上げ、ひじをしっかり曲げて開手する。 引き手となる左手は打ち手のわきの下に手を伏せて構え、右手の打ちと同時に引き手に戻す。 |
|
2. 打ち手は、ひじと手首を回転させながら水平に回し、目標であるこめかみへ手刀で打つ。 打った時には手刀は水平になっており、手首と手刀は直角に近いくらいに曲げる。 |
|
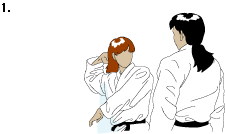 |
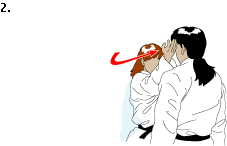 |
▼内手刀打ち ・・・手刀打ちを内側から打つ打ち方である。
1. 引き手側の肩の上で背拳を相手に見せないようにしてねじり、引き手は打ち手のわきの下に背を上に向けて構える。 |
|
2. 次に左手の手首をねじりながらもどし、内側に弧を描くようにしながら相手のこめかみへ攻撃する。 |
|
この打ちの力の根源は、腰の回転と同時に手首のひねりによるスナップである。腕だけで打つと力が入らず効力がない。 |
|
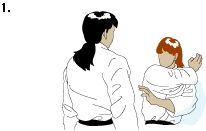 |
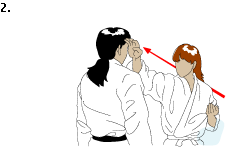 |
▼鉄ツイ打ち(拳ツイ打ち)・・・こぶしを握った時の鉄ツイ部で、上から真下に落とした打ち方である。
打ち落としは、腕をくの字に曲げたまま打ち落とし、わきを絞めて力が肩から逃げないようにする。 |
|
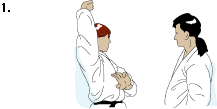 |
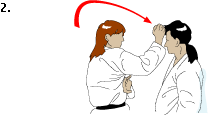 |
▼熊手打ち
外手刀打ちと同じような形で打つが、手刀打ちは手首の水平移動によるものであるが、 熊手打ちは手首を背小手から内小手方向へスナップをきかせて打つ。 すなわち、当たる直前までこぶしは自分の方へ折り曲げておき、当てると同時に背小手と背拳を張るようにして打つ。 |
|
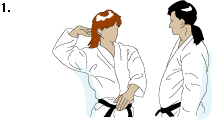 |
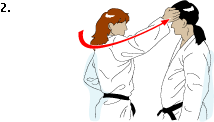 |
▼腕刀打ち ・・・内手刀打ちと同じようにして打つ打ち方であるが、使用部は裏小手部の腕である。
手刀のように手首の回転によらず、ひじ関節を利用して腕全体で人中付近を攻撃する。 打ち方も、腕を相手の顔面と直角にして水平に押すようにして打ち、腕全体のスナップをきかせる。 接近戦などでたびたび使用される技である。 |
|
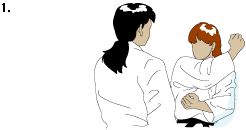 |
 |
▼鶏頭打ち・・・
鶏頭を使用して下から上へ打つ方法である。目標は使用のしかたによっていろいろ異なるが、ここではあごを目標にしている。
打ち方は手首を下へ折り曲げて構え、2で下から斜め上へ物を釣り上げるようにして打つ。 当てた時、手首は曲がっている(手首の回転を利用)。一見、鶴頭当てと間違いやすいから、その使い分けに注意する。 鶴頭打ちは下から上への攻撃の他に、振り打ちのようにしてこめかみを目標とする場合もある。 |
|
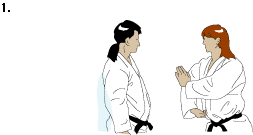 |
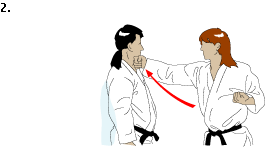 |
▼鳥嘴拳打ち・・・貫手を1つにまとめて、鳥のくちばしのようにして打つ打ち方で、ちょうど外手刀打ちのようにして打ち込む。
この打ち方は、鳥がくちばしで物をつつく打ち方と似ており、目標もこめかみの他に人中、目、のどなどがあげられる。 打ち方の軌跡は横からの曲線となり、手首のスナップをきかせて打つとよい。 |
|
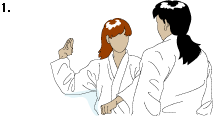 |
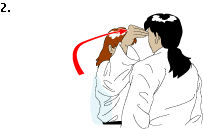 |
▼ひじ当て(正面)
1. 正拳突きの構えと同様に構える。 |
|
2. 右ひじを前方に突き上げ、ひじで相手のあごを攻撃する。 |
|
目標はあごのほかに水月へも可能であるが、ひじを突き上げる時小手部がひじから離れたり、 ひじを前へ押したりしたら効果がない。ひじを上げた時に、わきの絞めが甘くなりがちであるが、当てた状態の時、 手のひらが自分の耳に平行になっていないと、肩に力が入ってわきも甘くなる。 すなわち、ひじ当ては引き手からのこぶしの1/2回転のひねりが加わって威力が発揮されるのである。 |
|
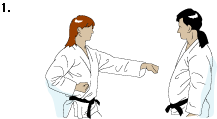 |
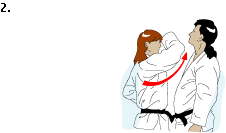 |
▼ひじ当て(背面)・・・後ろから組みつかれた場合のひじ当てであるが、主として水月を目標とする。
当て方は、引き手による時の力だけではなく、腰を後方に回転させてややそり身となりながら当てる。 この時、他方の手を補助として使用すると効果が大きい。 |
|
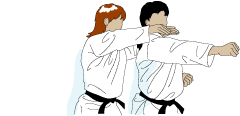 |
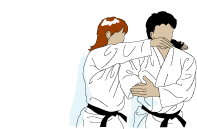 |
▼ひじ当て(落とし)・・・前から組みつかれた場合などに使用されるひじ当てで、目標は主として後頭部か背骨へ加える。
当て方はこぶしを握って上段に振りかぶり、目標に向かって体重を落とすようにする。 正面、背面のひじ当てと同じように、小手部をひじ関節からゆるめないことが大切である(図は省略)。 |
▼鶴頭当て・・・鶏頭打ちと同じようにして下から上へ突き上げる方法で、鶴頭部を使用する。
これは、腕の前後の運動を生かした当て方で、まっすぐ当てず、下から曲線を描いて相手のあごの真下から直角に当てるようにする。 |
|
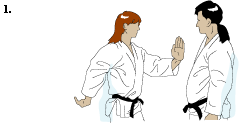 |
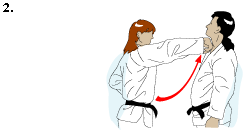 |
(3)蹴り技
▼下段蹴り(金的蹴り)
1. 蹴りの構え
右足を1歩後退させた半前屈の立ち方。両手はこぶしを握る。 |
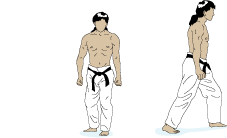 |
2. 右足膝を持ち上げる。
膝をしっかり曲げ、 腓( ひ )腹筋( ふくきん) (下腿にある屈筋)と太ももとが ぴったり密着していなければいけない。足首はまっすぐ伸ばしてつま先を落とす。 |
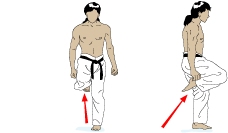 |
3. 膝から先をまっすぐ伸ばし、下段急所に対して背足部で蹴り上げる。
下段蹴りは、あまり高く蹴り上げる必要はなく、 自分の帯の高さに下から上へ押すようにして蹴り上げる。 |
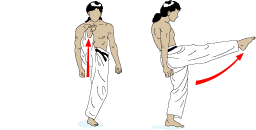 |
4. 蹴ってから1の構えに戻すが、1〜2と同じように3から2に戻り、 1の構えにする。 下段蹴りで使用する背足部は、自分にとっても急所であるから、 相手に受けられた場合は逆に攻撃されたと等しい結果となる。 そのため下段蹴りは、できるだけ速く、相手に受けられないように 蹴らなくてはならない。 速く蹴るためには、速く引き足を取るように心掛けるとよい。 下段蹴りは、試合においては危険防止の意味から禁止技となっている 。 |
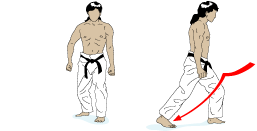 |
▼前蹴り
1. 蹴りの構え。
|
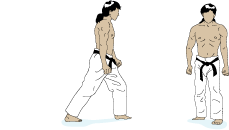 |
2. 膝を上げる。つま先は上げる。
|
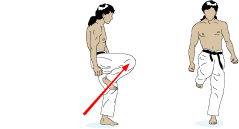 |
3. 前蹴り。
前蹴りは正面に対して虎趾の部分で蹴るが、目標は中段部、上段部とに 分けられる。蹴る方向は下から上へ蹴り上げるのではなく、 45度の角度で蹴り込む形となる。下肢構造から見て、蹴りを突き技のように まっすぐ前方へ蹴り出すことはできないから、膝と腰の調整をもって できるだけまっすぐ蹴るようにする。 蹴りの高さは、この膝の高さによってほぼ決まるが、2から3への 腰の入れによって、1〜2までの反動を利用して高さを決めることもできる。 蹴ったときの足首はまっすぐで、つま先だけは上を向いている。 |
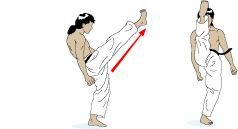 |
4. 引き足を速く取って、蹴りの構えに戻る。 3の蹴りから2の動作(図は省略)をしてから4の構えに戻る。 |
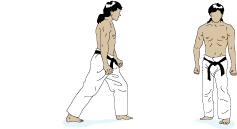 |
▼横蹴り
1. 蹴りの構え
|
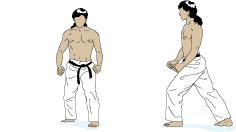 |
2. 蹴り足を膝と水平に真横に上げると同時に支えている足の踵を 横にして、蹴りやすいようにする。 膝を上げた時の蹴り足の足首はまっすぐで、つま先だけ上がっている。 |
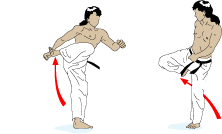 |
3. 2の膝を基点にして足を伸ばし、横の方から蹴る。
蹴り切った時、上半身を倒さない。 また、支えている足も、バランスを取るために少し曲げる。 足首はまっすぐにし、つま先を曲げて虎趾の部分で当てるようにする。 目標の高さは、2の膝から足首までの角度によって決まる。 膝と足首とが水平ならば蹴りの高さは膝の高さと等しくなり、 2の状態で膝と足首とが斜めとなっていれば、 蹴りは膝からまっすぐ伸びるから上段部への蹴りとなる。 |
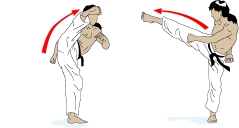 |
4. 引き足を引いて2の姿勢を取り、1の構えに戻る。 |
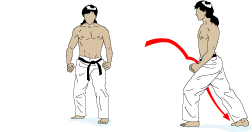 |
▼関節蹴り
1. 蹴りの構え
|
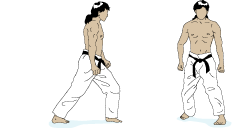 |
2. 蹴る方の足の膝を正面に持ち上げ、足は内側に曲げる。 つま先は親指を上に曲げ、他4指を下へ落として、 足刀部と足首をまっすぐにしながら、目標方向へ向ける。 |
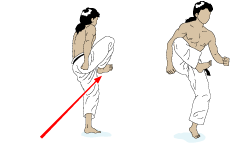 |
3. 関節蹴り
2の膝を斜め前方へ落とし、足刀部で関節を外側から攻撃する。 蹴りは、上から関節に乗っかるようにして蹴り込む。 |
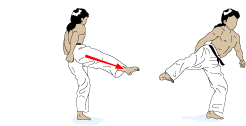 |
4. 3の蹴りの後、できるだけ速く引き足を取り、2の姿勢に戻って から4の構えを取る。 この蹴りはあまり腰を入れてはならず、また引き足は速くなければならない。 試合での使用は禁じられている。 |
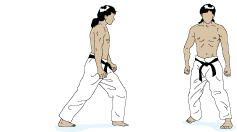 |
▼足刀蹴り
1. 蹴りの構え
|
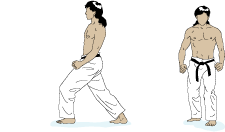 |
2. 支える足の踵を相手側にひねって、蹴り足の膝を前方に持ち上げる (関節蹴りのように高く上げる必要はない)。 |
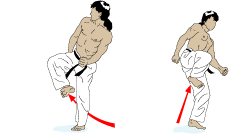 |
3. 正面に対して踵で蹴るようにして、足刀部を目標に直角に当てる。
足刀蹴りは、床から上に持ち上げる蹴りではなく、 腰からまっすぐ前方に蹴り込まなければいけない。 |
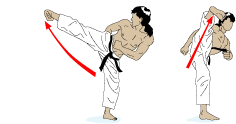 |
4. 引き足を取って2の姿勢に戻り、4の構えを取る。 |
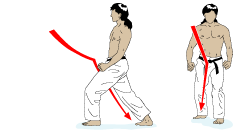 |
▼後ろ蹴り
1. 蹴りの構え |
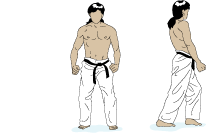 |
2. 軸となる左足を回転させて真後ろを向き、 踵で臀(でん)部(ぶ)を蹴り上げるようにして足を持ち上げる。 |
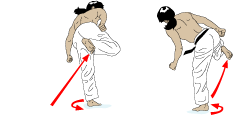 |
3. そのまま膝を真後ろに伸ばし、水月部、のど、顔面などへ まっすぐ蹴りを放つ。蹴りの使用部分は虎趾の場合と踵の場合とがある。 |
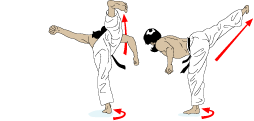 |
4. 3から2の姿勢になって4の構えに戻る。 この蹴りは、一般的に使用される蹴りではなく、 目標をはずすと非常に不利な状態になる。 |
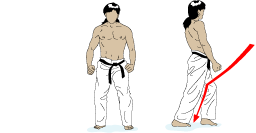 |
▼膝蹴り
1. 蹴りの構え
|
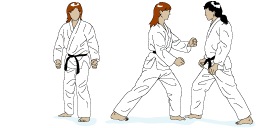 |
2. 後ろ足を上げて蹴りの準備
|
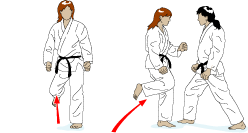 |
3. 膝蹴り
膝蹴りは接近戦において有効な攻撃力となる。 |
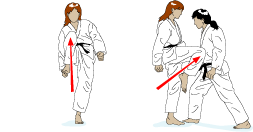 |
4. 腰を後ろに引くようにして膝を下ろし、蹴りの構えに戻る。 目標は下段急所か水月部になる。 膝蹴りは、腰から一番近い部位を使用するため、蹴りの威力としては 一番強い。遠距離攻撃は危険性があるので、 両手で相手の肩等をつかまえれば、より的確で強力な蹴りとなる。 |
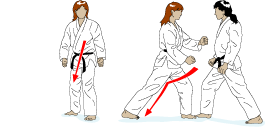 |
▼頭突き
これは極度な接近戦となった場合、手技、足技が使用できなくなった時に しばしば使わる攻撃で、額による顔面攻撃である。 両手で掴んでいる相手の両肩を、手前に引き込むようにして頭突きを決めると、 より効果的に使用できる。頭突きの目標は、顔面の眉間、鼻頭、人中などである。 |
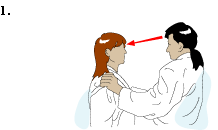 |
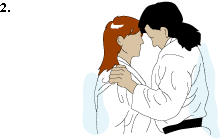 |