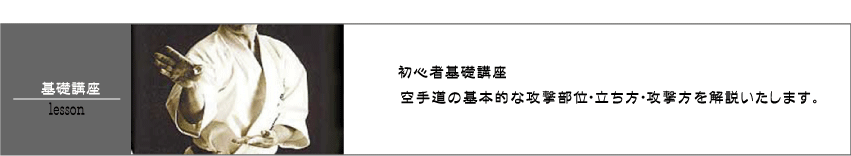
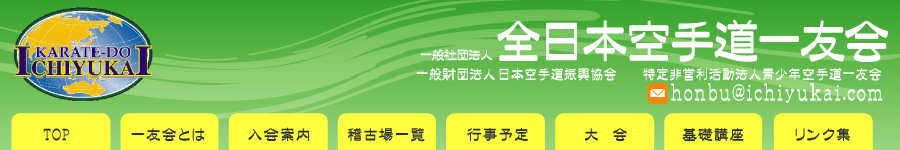
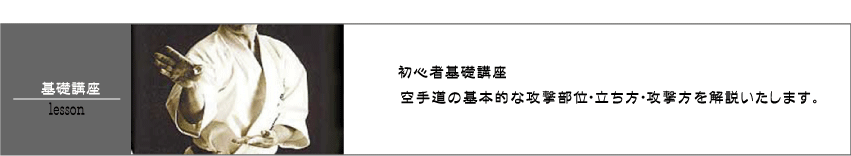
●基礎講座メニュー
| 基本 | |||
|---|---|---|---|
| ●攻撃部位 | ●立ち方 | ●攻撃技 | ●受け方 |
| 形 | |||
| ●形とは | ●太極上段 | ●撃砕第一 (形の分解) | |
●基本-攻撃部位
空手で使用する個所
| 身体図 | |||
|---|---|---|---|
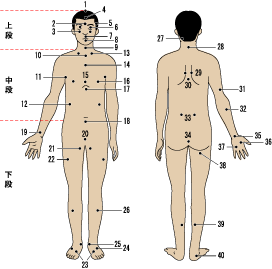 |
1.聖門(せいもん) | 17.水月(すいげつ) | 29.早打(はやうち) |
| 2.鳥兎(うと) | 18.明星(みょうじょう) | 30. 活殺(かっさつ) | |
| 3.晴雲(せいうん) | 19.内尺沢(うちしゃくたく) | 31.腕馴(わんしゅ) | |
| 4.天倒(てんとう) | 20.金的(きんてき) | 32.肘詰(ひじづめ) | |
| 5.霞(かすみ) | 21.夜光(やこう) | 33.後電光(うしろでんこう) | |
| 6.眼青(がんせい) | 22.伏兎(ふと) | 34.尾底(びで) | |
| 7.人中(じんちゅう) | 23.甲利(こうり) | 35.外尺沢(そとしゃくたく) | |
| 8.下昆(かこん) | 24.草陰(そういん) | 36.開握(かいあく) | |
| 9.三日月(みかづき) | 25.内課(ないか) | 37.手甲(しゅこう) | |
| 10.秘中(ひちゅう) | 26.向骨(むこうずね) | 38.後稲妻(うしろいなづま) | |
| 11.脇陰(わきかげ) | 27.独古(どっこ) | 39.草攣(くさづり) | |
| 12.稲妻(いなづま) | 28.顎中(けいちゅう) | 40.外課(がいか) | |
| 13.村雨(むらさめ) | |||
| 14.壇中(だんちゅう) | |||
| 15.胸尖(きょうせん) | |||
| 16.雁下(がんか) | |||
(1) 手の部位
01. 正拳 (せいけん) |
5指を全部折り曲げて物を握りしめた形である。 手のひらに空間が出来ないように肉を絞るように固く握り 親指でしっかり止める。 腕と手の甲とは水平になり、横から見た時に甲とこぶしとが 直角になっていなければいけない。 |
-01.gif) |
|---|---|---|
02. 裏拳 (うらけん) |
正拳と同じ握り方であるが、使用部位は人さし指、 中指の第3関節頭で、上に突き上げるようにして当てる場合と、 手首のスナップを使って当てる場合とがある。
|
-02.gif) |
03. 拳ツイ (けんツイ) |
正拳を握ってこぶしを縦にした場合の小指と手首までの 中間部筋肉をいう。 この部位を、金槌と同じように使用する。 手首とこぶしとは一体になって固定されていなければいけない。 |
-03.gif) |
04. 中高一本拳 (なかだか いっぽんけん) |
正拳の握りから中指の1指を飛び出させ、 親指で中指の第1関節部を押える。 攻撃に使用される部位は、中指第2関節部で、 当たる部位がせまいことから、 急所もせまい部分を対象としている。 たとえば、人中、のど、水月などへの攻撃として 使用されると効果がある。 |
-04.gif) |
05. 一本拳 (いっぽんけん) |
中高一本拳が中指を使用するのに対して、一本拳は、 人さし指の第2関節部を使用する。 正拳の握りから人さし指のみをゆるめ、 第2関節部を飛び出させ、 親指は人さし指の第2関節部を押える。 |
-05.gif) |
06. 開甲拳 (かいこうけん) |
5指を全部折り曲げて物を握りしめた形である。 手のひらに空間が出来ないように肉を絞るように 固く握り親指でしっかり止める。 腕と手の甲とは水平になり、横から見た時に甲とこぶしとが 直角になっていなければいけない。 |
-06.gif) |
07. 手刀 (しゅとう) |
拳ツイ(鉄ツイ)の手を開いた状態で、 小指の第3関節から手首との間の筋肉をいう。 手を開いた時、指の間を広げることは危険なので、 互いに指を密着させ、親指は第1関節をしっかり曲げて、 第2関節を外側に張るようにする。 |
-07.gif) |
08. 背刀 (はいとう) |
手刀に対して裏側を背刀と呼ぶが、 手刀が手のひらを外側に張ったのとは逆に、 親指は第1、第2関節とも折り曲げ、 人さし指の第2関節から親指の第2関節の間を使用する。 親指に力を入れることによって、親指と人さし指との間に 筋肉が盛り上がり、その部位を鍛錬することが出来る。 |
-08.gif) |
09. 背手 (はいしゅ) |
握り方は開甲拳のように握り、 人さし指、中指の第3関節頭と手の甲を使用する。 |
-09.gif) |
10. 貫手 (ぬきて) |
手刀と同じように手を開くが、指はまっすぐに伸ばす。 使用部位は指の先端であるが、図のように中指を中心と する場合と、小指、親指を除いた他の3指の先端をそろえて 使用する場合とがある。 使用される場所はせまい急所とか、柔らかい部分への 攻撃として生かされる。 |
-10.gif) |
11. 一本貫手 (いっぽんぬきて) |
貫手の一本指の場合であるが、 人さし指を使用するのが普通である。 現在、技として使用される場合はほとんどない。 |
-11.gif) |
12. 二本貫手 (にほんぬきて) |
人さし指、中指の貫手で、 親指は中指と薬指との中間を押え、 使用する2指はまっすぐ伸ばす。 主として、両眼への攻撃として使用される。 |
-12.gif) |
13. 底掌/掌底 (ていしょう/ しょうてい) |
手のひら下部、すなわち親指の第2関節筋肉と小指側、 手刀表部の筋肉とが使用される部位で、 攻防のいずれにも適用される。 筋肉に力を入れるためには、親指と小指をしっかり曲げ、 手のひらを極力広げるようにすることが大切である。 手は思いきり立てて、手首と手とが直角になるようにする。 |
-13.gif) |
14. 鶴頭 (かくとう) |
手首を下のほうに曲げて、手のひらを閉じ、 親指は中指と薬指のつけ根を押える。 使用部位は曲げられた手首からやや甲の方の頭部である。 ちょうど、鶴の頭を思わせる形から鶴頭と呼ばれている。 底掌と同じように攻防いずれにも使用される。 |
-14.gif) |
15. 鶏頭 (けいとう) |
親指の第2関節頭を使用するもので、 鶏の頭に似ていることから鶏頭と呼ぶ。 背刀が親指を内側に折るのに対して、 鶏頭は親指を上に突起させ、手のひらは張らずに 内側に閉じるようにする。 |
-15.gif) |
16. 鳥嘴拳 (ちょうしけん) |
鷲のくちばしのように鋭くとがり、 5指をまっすぐ伸ばしてそれぞれの先端が 貫手のように直線にならず、 ひとたばねにたばねたような形にする。 |
-16.gif) |
17. 腕刀 (わんとう) |
裏小手部を使用しての攻撃に用いる名称で、 手は開いても握ってもよい。 主として接近した際に、首筋への攻撃に対して 使用される部位である。 |
-17.gif) |
18. 猿臂/ひじ (えんび) |
腕関節のひじの事であるが、 腕を関節部から思いきり曲げてこぶしを堅く握り、 こぶしは小手と水平にしなければいけない。 ひじは少し内側にずれると急所になるから 使用の際には気をつける。 |
-18.gif) |
19. 熊手 (くまで) |
開甲拳と同じように握り、親指を除いた4指の第1関節を 使用する。 各指の第3関節は外側に強く張り、 “打ち”として使用する場合には当てた瞬間に各指、 第3関節の折り曲げる力をも加える。 |
-19.gif) |
20. 虎口 (ここう) |
親指と人さし指とを開き、 その間を虎の口のように丸く開いた部分で、 のどへの攻撃に活用され、 突きとして使用する場合には、突いた後、 のどを絞める働きもする。 |
-20.gif) |
21. 指鋏 (ゆびばさみ) |
親指、人さし指の第1関節を横に開き、 中指と薬指、小指の関節を縦に並べた握り方で、 虎口と同じようにのどへの攻撃に使用するのは、 のどを絞めるための働きではなく、 のどぼとけをはさみつぶすための突きに 使用される部位である。 |
-21.gif) |
22. 表小手 (おもてこて) |
ひじから手首へかけての親指側で、外腕部のことである。 防御を主とした部位で、こぶしに力を入れることによって 外腕部の筋肉にも力が入る。 |
-22.gif) |
23. 裏小手 (うらこて) |
ひじから手首にかけての小指側で内腕部のことである。 |
-23.gif) |
24. 内小手 (うちこて) |
背小手の内側で、ひじから手首にかけての 手のひらの側である。 背小手と同じようにあまり使用されない。 |
-24.gif) |
(2) 足の部位
01. 虎趾/上足底 (こし/じょうそくてい) |
つま先の裏側で指のつけ根部分であるが、 指が当たらないように全指上側にそり上げなければ いけない。ちょうど、つま先で立った時に 床に残る足趾が、虎の足趾に似ているので 虎趾と呼ばれる。虎趾を使用しての蹴りは、 足首をもまっすぐに伸ばし、虎趾の部分が 足とまっすぐ連結されなければいけない。 |
-01.gif) |
|---|---|---|
02. 足刀 (そくとう) |
足の小指からかかとの間で、 親指を持ち上げ他の4指を下げることによって、 刀のように鋭くなる。足刀の使用による蹴りも 足と足刀部とが直角になるようにする (かかとを押し出すようにするとよい)。 |
-02.gif) |
03. 背足 (はいそく) |
足の甲の部分で、つま先を下へ折るようにして、 足甲を張るようにすればよい。 アキレス腱を伸ばさず、かかとを引き 逆に絞めるようにするとよい。 背足部は足の急所でもあるから、 攻撃に使用する時に、逆に痛めないように気をつける。 |
-03.gif) |
04. 踵(かかと)・ 下足底(かそくてい) |
全部位を通して、一番堅いところでもある。 踵を蹴りに使用する場合には足首を上に曲げ、 アキレス腱を伸ばして脚筋と連結させる。 アキレス腱の下の後ろ踵も後方への 蹴り上げ式の蹴りに使用される。 |
-04.gif) |
05. 趾頭 (しとう) |
足の指先のことであるが、 図のように親指と人さし指を並べる方法と、 親指で人さし指を上から押えて親指1本のつま先を 使用する場合とがある。 蹴りとして使用する場合には、のどとか水月への 柔らかくせまい部分への急所に使用される。 |
-05.gif) |
06. 膝頭 (ひざがしら) |
膝関節部をいう。 接近した際の攻撃蹴りとして使用した場合、 関節内の炎症を起こすこともあるから気をつける。 |
-06.gif) |
07. 額 (ひたい) |
頭突きとしてだけ使う個所であるが、 額そのものが急所ともいえる部位であるから 極度な鍛錬練習は感心しない。 額を使用しての攻撃は、当然、額よりも弱い部分への 攻撃としてしか使用できないため、 接近した場合の顔面への攻撃にしばしば用いる。 |
-07.gif) |